【完全ガイド】中小企業の脱炭素経営とは?
必要な理由・メリット・具体的な取り組み方を徹底解説!
何から始める?中小企業の脱炭素経営
INDEX
そもそも「脱炭素経営」とは?
脱炭素経営
脱炭素経営とは、温室効果ガス(主にCO₂)の排出を最小限に抑え、実質的な排出ゼロ(カーボンニュートラル)を目指す経営方針のことです。製造工程や物流だけでなく、オフィスのエネルギー使用やサプライチェーンに至るまで、あらゆる業務の中でCO₂削減の余地を検討し、実践します。またそれを情報開示する姿勢も求められています。
近年では金融機関や投資家が企業を評価する基準のひとつとして脱炭素経営を挙げるほど、企業価値を向上させる重要な要素となっています。
カーボンニュートラルと企業の役割
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量から吸収量(森林による吸収やカーボンクレジット購入による間接的吸収)を差し引いた実質的な排出量をゼロにするという概念です。日本政府は2050年にカーボンニュートラルを実現することを宣言しており、現在では国を挙げた重要な政策のひとつとなっています。
この政策を実現するためには、家庭や自治体だけでなく、あらゆる企業の参画が必要不可欠です。企業活動は電力の使用や原料調達・輸送におけるCO₂排出要因が多く、削減インパクトが非常に大きいからです。
これらはもちろん環境保護のための自主的な取り組みであることが望ましいですが、近年では自治体から省エネ基準の適用を要請される場合や、入札における条件としてLED照明や高効率空調の使用を必須化される場合もあり、企業の脱炭素経営は努力義務から事実上の必須対応とされるケースも増加しています。
2025年4月には改正建築物省エネ法が施行され、原則としてすべての建築物について省エネ基準への適合が義務化されました。(建築物省エネ法 | 国土交通省)
また、各地方自治体でも、企業に対して様々な省エネ基準を策定している場合があります。
以下に、具体的な自治体の要請事例をあげましたので、参考にしてみてください。
東京都:地球温暖化対策報告書制度(中小規模事業所)
東京都内の中小企業を対象に、各事業所のCO₂排出量と省エネ等の地球温暖化対策の状況を都に報告する制度です。
<参考リンク>
中小規模事業所における対策|地球環境・エネルギー|東京都環境局
京都市:2050京からCO₂ゼロ条例(京都市地球温暖化対策条例)
京都市は京都議定書が採択された都市として地球温暖化対策のイニシアチブをとるため、この条例を制定しました。この条例は、地球温暖化対策において、事業者や市民などさまざまな主体の責務や、それに基づく自主的かつ積極的な取り組みを定めており、2050年にCO₂排出実質ゼロを目指しています。
<参考リンク>
京都市:2050京からCO₂ゼロ条例(京都市地球温暖化対策条例)
横浜市・大阪市など:公共調達における省エネ基準の要求
横浜市は公共建築物における環境配慮基準を定めています。
また大阪市では「大阪市グリーン調達方針」として庁内における環境負荷の少ない物品の購入やリサイクル製品の調達の推進を図る施策を実施しています。
これらは自治体に対する「要請」ではありませんが、公共機関がまず環境配慮について手本を示し、広く脱炭素社会の実現を目指す意図があります。
<参考リンク>
公共建築物における環境配慮基準 横浜市
大阪市グリーン調達方針のページ/大阪市のホームページ
中小企業にも求められる脱炭素経営の重要性
これまでは、「脱炭素経営=大企業の取り組み」というイメージがあったかもしれません。
しかし近年では、急速に中小企業にも脱炭素経営への参加が求められるようになっています。
その背景には、国際的な潮流や社会的な期待の高まりに加え、取引先の調達基準の変化や環境意識の高い消費者ニーズといった、より高度で具体的な外部からの要請があるからです。
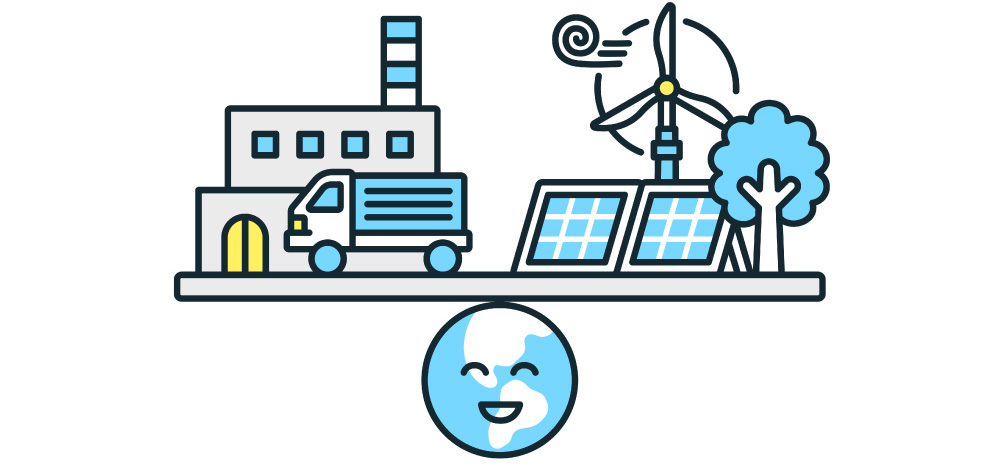
中小企業が脱炭素経営に取り組むべき理由
中小企業にとって脱炭素経営は経営の持続可能性を左右する重要な課題となっています。ここからは、なぜ中小企業が脱炭素経営に取り組むべきなのか、具体的な理由を5つの視点から解説します。
規制・政策への対応
前章でも述べた通り、国や自治体は脱炭素社会の実現に向けて、省エネ法や関連制度の強化を進めています。
省エネ法は、すべての事業者を対象にしていますが、特にエネルギー使用量の多い一部の事業者には、より厳格な義務が課せられています。
省エネ法において規制の対象となるのは、主に以下の5区分の事業者です。
①工場等の設備を有する事業者
②貨物・旅客の運送を行う運送事業者
③荷主(製造業・小売業など)
④機械器具(自動車、家電、建材など)の製造・輸入事業者
⑤家電製品などの小売事業者、およびエネルギーの小売事業者
このうち、年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上となる事業者は、「特定事業者」に該当します。
特定事業者には、以下のような義務が法律によって定められています。
・定期報告書の提出(毎年)
・中長期的な省エネ計画の策定と提出
・エネルギー管理体制の整備
・改善が不十分な場合の行政対応
これらに対しては行政指導や勧告が行われることもあり、達成可能性のある現実的な計画が必要です。
取引・市場競争での優位性
中小企業が脱炭素経営に取り組むことは、単にサステナブルな経営に繋がるというだけでなく、今後の取引維持や新規開拓にも大きくかかわってきます。
実際に、大手企業の多くが自社のサプライチェーンに対して温室効果ガス(GHG)の排出量把握と削減努力を求めるようになっています。特に上場企業やグローバル企業ではサステナビリティ報告(TCFD、CDP、ESGレポートなど)の中で、Scope3(間接排出)への対応が強く問われるようになっており、それに伴って中小企業の取引先にも環境データの提出や脱炭素対応が求められています。
Scope3(間接排出)とは…企業(自社)の活動に関連する他社の温室効果ガス(GHG)排出を指します。たとえば、部品や原材料の調達、外部業者による輸送、消費者による製品の使用や廃棄などです。
これに対し、Scope1は自社が直接排出する分、Scope2は購入した電力などによる間接排出を指します。Scope3は企業の排出全体の7〜9割を占めることもあり、中小企業が排出量データの提供や環境配慮の方針を持つことが、取引継続の前提条件になるケースが増えているのです。
こうした動きに拍車をかけているのが、EU(欧州連合)のCBAM導入です。
CBAMとはCarbon Border Adjustment Mechanism:炭素国境調整措置の略であり、鉄鋼、アルミ、肥料、セメントなどの高炭素排出産業を中心にEU域外から輸入される製品に対して「炭素コスト」を上乗せする制度です。
CBAMは2026年には本格運用が予定されており、対象品目は今後も拡大予定です。これによって日本の中小企業であっても欧州企業と取引する際には製品に含まれる炭素排出量の把握と提示が必須になります。またそれに伴う炭素コストも支払う必要があります。
CBAMに類似する炭素税はアメリカ・カナダでも検討が進んでおり、脱炭素に対応しないことはすなわちグローバル市場の競争から取り残されるリスクを示唆しています。
上記のような社会的背景が強まっている以上、対応できない場合は取引先から外されるリスクも考えなくてはなりません。しかし、脱炭素経営に対して積極的に対応ができれば、「環境に配慮しているパートナー」として信頼を得られるチャンスでもあります。脱炭素経営は取り組まなければいけない必須課題であるとともに、競合他社との差別化を図る重要な手段でもあるのです。
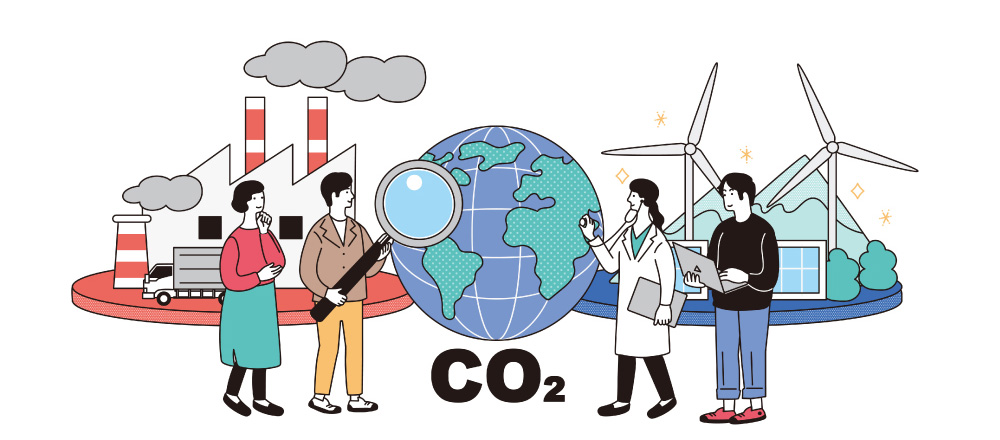
コスト削減と経営効率の向上
①電気代の削減
最もわかりやすいのが電気代の削減です。電気代の高騰が続く中、太陽光発電などの再エネ導入は経費の変動を低減する重要な役割を果たします。
PPAモデルを活用すれば初期費用を抑えることも可能です。脱炭素経営へ向けての大きな第一歩を踏み出すことができます。
②高効率設備導入によるコスト削減
工場の設備更新も立派な脱炭素アクションのひとつです。設備更新を行うことにより年間の電気代が大幅に軽減したという例もあります。また、断熱材や遮熱塗料の導入でも冷暖房コストを削減することができます。
これらは初期投資こそ必要ですが、数年で元が取れる場合も多く、長期的に利益を生み出す省エネとなります。
③IT化による経営効率向上
経営効率の向上と脱炭素を両立させる施策として注目したいのがIT化です。例えば出張を減らしてテレワークやクラウド業務を推進することでCO₂の排出量だけではなく交通費や出張費などの経費圧縮にもつながります。社内の紙資料や回覧文書をペーパーレス化・電子承認フローに切り替えることで、印刷費や保管スペースの削減だけでなく、事務作業の効率化や労働生産性の向上にもつながります。こうした取り組みはひとつひとつのインパクトは小さいですが多くの社員の省エネ意識を高め、業務の無駄を見直す契機ともなります。
結果として、脱炭素と業務効率の両方を持続的に高めていくための中長期的な基盤づくりにもつながります。
企業価値向上
脱炭素経営は企業価値の向上に役立ちますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。この章では中小企業における脱炭素経営の具体的な企業メリットについて解説します。
①顧客や地域社会からの信頼向上
近年では消費者が製品やサービスに対して「どのように作られているか」にまで関心を持ち、意見するシーンが多く見受けられます。
製品の背景にある企業の姿勢や倫理観に注目し、共感できる企業を選ぶ傾向が強まっているのです。
こうした流れの中で、例えば環境意識の高い製品を生産している企業は、環境に責任をもつ誠実なブランドとして選ばれやすくなります。また、企業ブランドの向上にもつながります。特にローカルビジネスにおいては地域社会とのつながりが重視されるため、環境負荷を減らす取り組みは地元住民や行政からの信頼も得やすくなります。
②融資や補助金での加点
金融機関においても、脱炭素経営やESG経営は評価のポイントです。環境に配慮し、持続可能な未来を追求する姿勢は資金調達の優遇要因になります。さらに、省エネ設備導入や再エネ活用の補助金申請においても、普段からの脱炭素への取り組みは評価項目としてプラスに働きます。「持続可能性」が必要不可欠である今、環境に配慮せずに経済メリットだけを追う施策は求められていないのです。
③採用力の向上
近年は特に若い世代を中心に、企業の環境・社会への姿勢を重視する求職者が増えています。
脱炭素経営を実践する企業は、「社会課題に向き合う未来志向の会社」として認識されやすく、採用活動においても優位に立つことができるのです。また、社内でも「環境に配慮している」「意味のある取り組みに関われている」という意識の芽生えは、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上にもつながります。
採用力の向上が企業価値の向上につながることは言わずもがなです。このような背景から、従業員レベルでの省エネ施策も重要な脱炭素経営の一つとして考えられています。

支援制度・補助金の活用が可能
脱炭素経営は「初期費用がかかりそう」「コストがかかりそう」。これは多くの企業が最初に感じる正直な懸念です。
しかしカーボンニュートラルを国が全力で推し進めている今、補助金や支援制度は非常に充実しており、これを活用しない手はありません。
中小企業に対しても脱炭素や省エネルギーを目的とした設備投資や業務改善には初期投資の負担を軽減する仕組みが多数用意されています。
以下は各省庁から発表されている支援の一例です。国だけではなく自治体での支援が用意されている場合もありますので、気になる方はぜひ管轄の自治体にお問い合わせください。
環境省 | 令和7年度予算 及び 令和6年度補正予算 脱炭素化事業一覧
令和7年度予算 及び 令和6年度補正予算 脱炭素化事業一覧 - エネ特ポータル|環境省
経済産業省(資源エネルギー庁) | 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
各種支援制度 | 省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト
<参考リンク>
中小企業の脱炭素化投資を後押し!カーボンニュートラル投資促進税制がリニューアル|エネこれ|資源エネルギー庁
中小企業におすすめの脱炭素施策7選
この章では中小企業がトライしやすい具体的な脱炭素施策について解説します。 補助金の活用も視野に入れながら検討を進めてみてください。
① 省エネルギー設備への更新(空調管理など)
古くなった照明や空調機器を高効率型に切り替えるだけでも、電気使用量の大幅削減が期待できます。
空調機器や給湯設備を見直すだけでも改善が見込めますし、BEMSと呼ばれるビルエネルギー管理システムを導入することでエネルギーの使用量を可視化し、電力の制御(ピークカット)や最適化を目指すことができます。BEMSは経済産業省・環境省などが積極的に導入を支援しており、補助金の対象にもなりやすい施策です。導入コストの1/2〜2/3が補助される場合もあります。
② 再生可能エネルギーの活用(太陽光発電・PPAモデル)
太陽光発電システムを導入すれば、日中の電力を自社でまかなうことで電力コストを削減できるだけでなく、CO₂排出量の削減にも大きく貢献できます。
特に、夏場の空調など電力消費が多い時間帯に自家消費すれば、電力単価の高騰対策としても有効です。
初期投資が不要な「PPAモデル(第三者所有モデル)」も活用すれば、資金面のハードルを下げて導入できます。
③ グリーン購入の推進
グリーン購入とは、製品やサービスを選ぶ際に、「価格や性能」だけでなく、環境への負荷が少ないものかどうかを考慮して購入する行動を指します。
「同じ”買う”なら、できるだけ環境に配慮された商品を選ぼう」という考え方で、国や自治体も推奨している取り組みです。 中小企業の日常業務では、文房具、コピー用紙、清掃用品、ユニフォーム、事務機器など、多くの物品を継続的に調達しています。
これらを「エコマーク」「グリーン購入法適合製品」「再生資源使用製品」などの環境配慮型商品に切り替えるだけで、間接的に温室効果ガスの排出削減に貢献することができます。
④ サプライチェーンの見直し(Scope1・2・3対応)
調達・輸送・販売などの各段階で排出されるCO₂を把握・削減する「Scope1〜3」対応は、企業の信頼性・取引維持に直結します。(「取引・市場競争での優位性」の章を参照)
中小企業も、取引先から排出量の報告や環境配慮の証明を求められるケースが増加しており、排出量の把握と見直しは必須です。
⑤ 環境認証の取得(エコアクション21・ISO14001など)
国や自治体も推奨する環境マネジメント認証(例:エコアクション21、ISO14001)を取得することで、脱炭素への「本気度」を明確に示すことができます。
これらの環境認証は第三者による審査や評価があるため、単なる自己申告以上の強い脱炭素アクションとして対外的な信頼獲得や補助金申請時の加点にもつながります。また、仕組みとして継続的な改善が義務付けられているため、将来性のある企業として企業のブランド価値を高めることができます。
⑥ IT活用による業務効率化(ペーパーレス化・テレワーク等)
出張を減らしてWeb会議やクラウド業務に切り替えたり、社内書類のペーパーレス化を進めたりすることで、CO₂排出削減と経費削減の両方を実現できます。社員の省エネ意識を高めるきっかけにもなり、中長期で大きな削減効果を積み上げることが可能です。
⑦ CO₂排出量の算定と削減計画の策定
まずは「どこでどれだけCO₂を出しているか」を把握することが脱炭素の第一歩となります。実はこれだけでも立派な脱炭素アクションです。
環境省のツールや診断サービスを活用し、可視化・定量化を行ったうえで、中期的な削減目標を立てましょう。補助金の申請や取引先との信頼関係強化にもつながります。
<参考リンク>
策定・実施マニュアル・ツール類|事務事業編|環境省 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト (環境省)

業種別脱炭素経営の成功事例
製造業の省エネ対策の事例
工場を保有することが多い製造業は、脱炭素経営に切り替えることで大きなインパクトのある業種です。特に老朽化した空調やコンプレッサーの高効率設備への更新は大きな脱炭素効果が期待できます。電気料金を大幅にカットできるだけでなく、騒音を低減したり、職場環境を改善できたりといった複合的なメリットもあります。
また、加熱調理機などから出た排熱を給湯や暖房に再利用する排熱回収や照明や空調を自動制御するシステム導入も取り組みやすい事例です。
設備更新やシステム導入が難しい場合は現状のCO₂排出量の把握だけでも意味がありますし、エネルギーの使用状況を分析することで、ピークカット・ピークシフトといった工程改善にもつながります。
これらの事例の実現には補助金を活用できる場合もあります。まずはどんなアクションが可能か検討することから始めてみましょう。
・省エネ診断
・工程改善
・空調・照明の最適化と自動制御
・排熱の再利用
・高効率設備への更新
サービス業の脱炭素施策の事例
飲食店、小売店、事務所、宿泊業などは、エネルギー使用量はそれほど多くないものの、取り組みやすさと社会的影響力が大きい業種です。
サービス業が取り組める脱炭素アクションについては、実行可能性と費用対効果を重視した施策が重要です。主に取り入れられているのが高効率空調設備や冷蔵機器の導入です。飲食店やスーパーなどでも省エネ設備に更新することで電気代を削減しながら脱炭素化に取り組む事例が増えています。
オフィス業務が中心のサービス業では、ペーパーレス化やクラウド活用による脱炭素化が進んでいます。オフィスのフリーアドレス化も使用スペースの最適化につながり、空調や照明のエネルギー使用量を削減できます。その上で照明や空調を自動制御(使用者がいない場合は切るなど)できればさらに効率的な運用が可能です。
電子契約書の導入も紙の使用量を削減できるため脱炭素に繋がります。
これらのアクションが難しい宿泊業や医療機関などでは、グリーン電力を購入するなどして間接的に脱炭素に貢献することができます。
・高効率空調設備への更新
・高効率冷蔵機器への更新
・ペーパーレス化やクラウド活用
・オフィスのフリーアドレス化
・電気や空調の自動制御
・グリーン電力の購入
中小企業向けの脱炭素支援策・優遇制度
脱炭素への取り組みを加速する補助金制度
脱炭素は中小企業にとっても避けて通れない重要な施策となっていますが、取り組みを加速させる補助金制度もまた充実しています。設備更新や再エネ導入、CO₂排出量の可視化など、あらゆる段階に応じた支援があるため、資金面の不安を和らげながら段階的に脱炭素を進めることが可能です。
補助金については以下の記事で詳しく解説しています。脱炭素経営にご興味のある方はぜひご覧ください。
まとめ | 脱炭素経営の第一歩を踏み出そう
いかがでしたでしょうか。脱炭素経営は、もはや一部の大企業や先進企業だけのものではありません。
国際的な規制強化や市場の変化、そして社会からの期待の高まりを背景に、中小企業にも確実に「脱炭素への対応」が求められる時代が到来しています。
照明や空調の見直し、業務のIT化、グリーン購入、再エネ導入など、できることから一歩ずつ取り組むことで、環境負荷を減らしながら経営の効率化や企業価値向上にもつなげていくことが可能です。
さらに、国や自治体の支援制度・補助金をうまく活用すれば、初期投資の負担を抑えながら持続可能な経営に向けた体制づくりも現実的に進められます。
オムロン フィールドエンジニアリングは、実際に補助金を活用した設備更新や再エネ導入の実績が数多くあります。脱炭素経営についてのご相談やエネルギー診断についてのご質問はいつでもお気軽にお問い合わせください。
【執筆者情報】

脱炭素ソリューション.com 編集部
脱炭素ソリューション.comが運営する「エネタメ」は、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社のエネルギーマネジメントに関する豊富な実績とノウハウを活かした専門的な情報や、再生可能エネルギー、蓄電池、災害対策、省エネソリューション、補助金などのコンテンツを中心に、脱炭素化/カーボン・ニュートラルの取り組みに役立つ情報を発信しています。







