FIP転(FIP移行・FIP転換)とは?
制度のメリット・デメリット、初期費用ゼロでFIP転できるサービスを徹底解説!
今さら聞けないFIP転について徹底解説!
INDEX
FIP転(FIP転換)とは?
そもそもFIP転(FIP転換)とは?FIT制度とFIP制度の違い
■政府から見たFIT制度とFIP制度
FIT(フィードインタリフ:Feed-in Tariff)制度は電気の固定価格買取制度です。政府はエネルギーの安定供給と環境保護の観点から、2012年にFIT制度をスタートさせました。FIT制度の導入により再エネ事業者は増加し、投資家も巻き込んだ売電事業が急速に拡大しました。
FIT制度は一定の成果を収めたといえますが、再エネが主力電源として電力市場に適応するにはまだまだ大きな課題があります。そのひとつに、電力を「固定価格」ではなく需要と供給に応じた「変動価格」で販売しなくてはならない、という点があります。
変動価格で販売するということは、せっかく作った電気を安く売らなければならない可能性があるということです。(もちろん逆に高く売れる可能性もあります。)基本的に電気は長期間保持しておくことができませんから、高く売れるタイミングから逆算して発電を行わなくてはなりません。しかし太陽光発電を中心とした再エネは自然条件に左右されるため、思った通りのタイミングで発電できないというジレンマがあります。
そこで変動価格に適応するための支援制度として導入されたのがFIP制度です。FIP制度は、電力市場の変動価格に「プレミアム」と呼ばれる補助額を追加することで再エネ事業者を支援しています。
■再エネ事業者から見たFIT制度とFIP制度
一方、再エネ発電事業者側からFIT制度とFIP制度を見てみましょう。FIT制度は発電した電気を固定価格で買い取ってもらえるという、とてもコストパフォーマンスの高い制度ですが、20年という買い取り期限があります。21年目に入ったFIT事業者は固定価格での買い取りが終了するため、新たに買い取ってもらえる電気事業者を探し、買い取り価格や買い取り条件を決める必要があります。価格は固定で買い取ってもらえる場合もありますが、多くの場合変動となりますから、再エネ事業者は必然的に電力価格を監視する手間やそれにともなう管理負担が増えることになります。
この手間や負担は発電事業者から見ると不安の種にもなっていますが、見方を変えれば発電事業に真剣に取り組むことで電力を有効活用できるチャンスとも捉えることができます。また、FIP制度によりプレミアムが発行されるため、FIP制度なしで発電事業者が売電する場合よりはかなり軽い負担で、次世代のエネルギー環境に適応することができます。
FIT制度からFIP制度に転換することを、FIP転と言います。現在ではFIT期限の満了(卒FIT)を待たずにFIP転する事業者が急速に増えています。
政府がFIP転換を進めている理由

前の章でもご説明しましたが、政府は再エネを「電力市場」つまり需要と供給によって価格が決まる電気のマーケットに適応させる必要があると考えています。再エネが電気市場に適応することができれば、採算性が高まり、主力電源への道が大きく切り開かれることとなります。FIP転換はそのための大切なステップです。
政府がFIP転換を進めている理由のひとつが、電力の安定供給です。日本のエネルギーはこれまで、石油をはじめとした石炭・天然ガスなどの化石燃料に大きく依存してきました。1970年代に起こったオイルショックをきっかけにエネルギー分散化の動きが進みましたが、東日本大震災以降、ふたたび化石燃料への依存度が高まっています。また今後も世界情勢の変化などからエネルギー資源を安定的に確保できない可能性が指摘されています。
電気料金は経済活動や家計にも大きな影響を与えることから、安価であることが望まれます。しかし、上記のように資源を海外に頼る日本では、どうしても発電コストが高くなります。一方で再エネは国内で発電できるという大きなメリットがあり、コストの安定化につながります。このため再エネは未来の日本になくてはならないエネルギーであり、政府にはFIP制度によって早期に再エネ主電源化を進め、電力の国内自給率を高める狙いがあります。
政府がFIP転換を進めているもうひとつの大きな理由が、環境問題です。地球温暖化対策は世界共通の課題です。課題解決の重要な方策として日本が掲げたのが、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」です。日本はカーボンニュートラルに向けて、2030年度までに温室効果ガスを大幅に(2013年度比で46%)減らさなくてはなりません。実現のための大きな柱として挙げられるのが、再生可能エネルギーの活用です。実は日本の温室効果ガス排出量の約84%がエネルギー起源のCO₂だと言われています。政府は、火力由来のエネルギーを再エネ由来のエネルギーに転換していくことが、カーボンニュートラルの実現に繋がると考えています。
さらに政府がFIP転換を進める理由として、国民負担の抑制があります。FIT制度下では、どの時間帯に売電しても固定価格で全量の電力買い取りを行っていました。買い取りのための資金は電気料金に転嫁されるため、どうしても国民負担は大きくなってしまいます。この状況を打破するため、政府は電力市場に即したFIP制度への転換をすすめています。
FIP転換には蓄電池が欠かせない
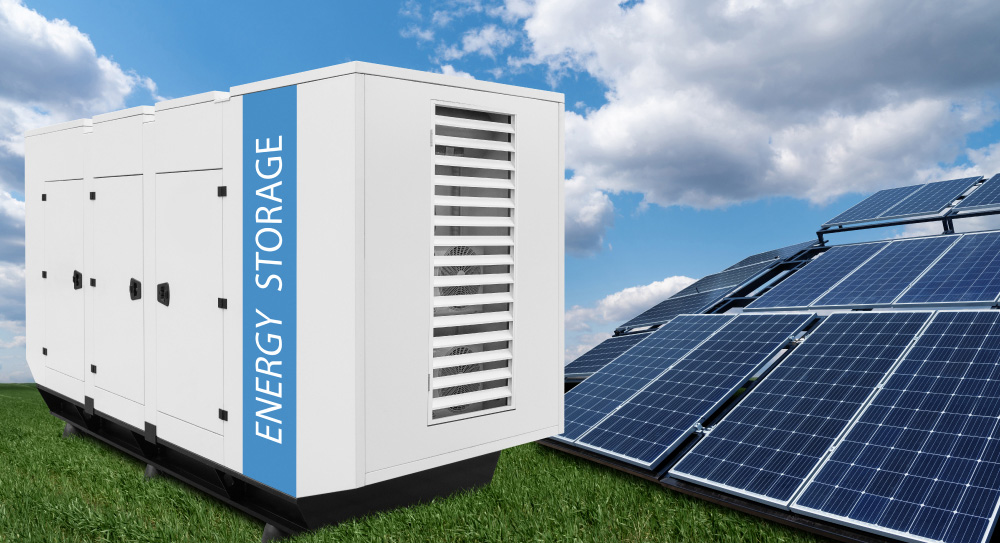
FIT制度下では、再エネ事業者は固定価格で電気を買い取ってもらえるため、需要と供給を考える必要はそれほど多くありませんでした。しかしFIT制度が終了し、FIP転を含めた固定買い取り制度のない状況の中で、再エネ由来の電力を電力市場の変動価格に合わせて売電し採算を取っていくためには、蓄電池が欠かせません。再エネ(特に太陽光発電)は発電のタイミングが自然条件に左右されるため一定の間電気をプールしておく必要があり、蓄電池の導入はほぼ必須です。
また、売電単価の安い時間帯には充電(蓄電)し、高い時間帯に放電するという効率的な売電コントロールを行うためにも蓄電池は大変重要です。
FIP転換(FIP移行)するための条件
FIP認定の対象となる電源種別・規模であること
太陽光発電でFIP制度の認定を受けるためには、50kW以上の発電設備が必要です。(50kW未満の発電設備はFIT制度が適用されます。)50kW~1,000kW未満の発電所はFIT制度とFIP制度を選択することが可能です。1,000kW以上の発電所は自動的にFIP制度が適用されます(FIT制度は選択できません)。
| 50kW未満の発電設備 | FIT制度 |
|---|---|
| 50kW〜1,000kW未満の発電設備 | FIT制度/FIP制度(選択可能) |
| 1,000kW以上の発電設備 | FIP制度 |
既にFIT認定を受けている再エネ発電事業であってもFIP移行は可能
すでにFIT認定を受けている発電事業者であっても、契約期間中(調達期間中)のFIPへの移行は可能です。FITからFIPへ移行する場合、FIPでの契約期間(交付期間)はFIT契約の残存期間となります。
FIP転換のメリット
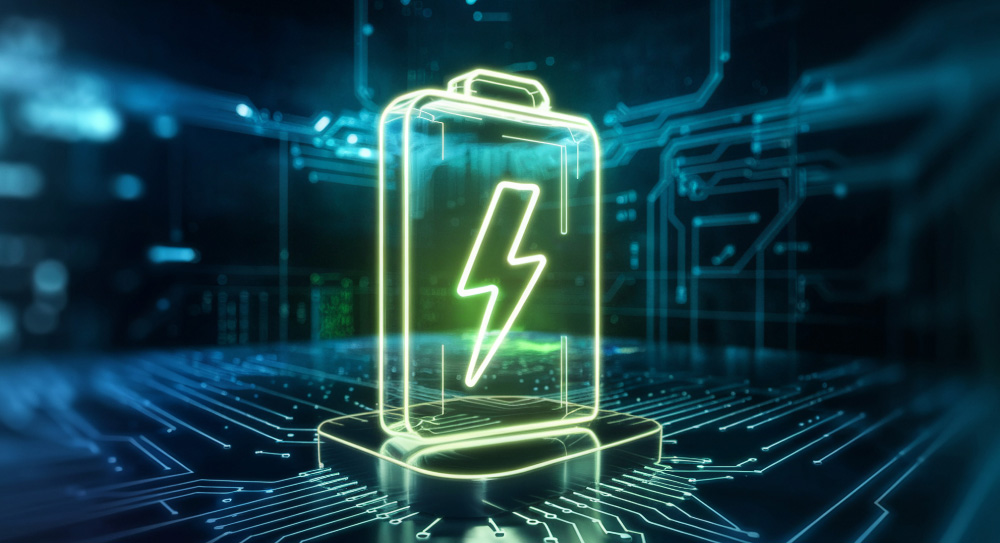
電力需要の高い時間帯を狙って高単価で売電できる
FIT制度では買い取り価格は固定でしたが、FIP制度では需要に応じて買い取り単価が変動するため、高単価のときに売電することで高い売電収入を得ることができます。
売電単価が高くなるのは、電力の需要が高まったときです。電力需要は猛暑・寒波などの季節・気象条件やイベント・休日などによって大きく変化します。一日の中でも人々の活動が活発になる昼過ぎ~夕方は電力需要のピークです。しかし太陽が上っている時間帯は再エネ電源による供給力もあるため需要はひっ迫するほどではありません。一方で、夕方から夜にかけてはまだ電力の需要が多い時間帯でありながら、太陽光発電の供給力が低下するため、需要は特に高まります。このような、電力の需要が高まったタイミングで売電をすることで高い収益を得ることができるのです。
小規模の発電事業者が高価格帯で売電を行うことは難しいのではないかと疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。その場合、アグリゲーターに電力の管理や販売を委託することでより簡易的・安定的に売電を続けることができます。
アグリゲーターとは、複数の発電事業者の電⼒をまとめて管理し、市場などに⼀括して供給する事業者です。アグリゲーターに管理を任せることで安定した電力の売り先を確保することができるとともに、発電計画の立案やインバランスコストの低減が期待できます。インバランスコストとは、発電が計画通りにいかなかった際のペナルティコスト(補償金)です。インバランスが発生しそうになったとき、アグリゲーターが電力を融通するコントロールを行い、インバランスを回避します。
出力制御の影響がFIT制度時よりも小さくなる
出力制御とは、電力の供給が需要を大きく上回ってしまったときに発電の量を制御することです。電力は需要と供給のバランスがとれていることが大変重要です。需要、もしくは供給に偏ってしまうと、バランスが崩れて大規模停電につながる恐れがあります。そのため供給過多になった際は一般送配電事業者(日本の各エリアで送電線・配電線を管理する事業者)が発電事業者に対して出力制御を行います。この出力制御は、電源ごとに制御順位が決められています。真っ先に抑制されるのが火力発電です。その後、余剰電力の送電などを適切に行ったうえで、それでも電力が余っている場合はバイオマス電源への出力制御→太陽光、風力への出力制御という順番で出力制御が行われます(優先給電ルール)。
政府は2024年12月2日に資源エネルギー庁系統ワーキンググループにおいて優先給電ルールの見直しを行いました。会議では出力制御の順番を、これまではFIT電源とFIP電源を区別せずに「バイオマス発電→太陽光・風力」という順番でしたが、早ければ2026年度中に「バイオマス発電(FIT電源→FIP電源)→太陽光・風力(FIT電源→FIP電源)」という順番に変更するとしました。これにより出力制御の影響は、FIT契約時よりもFIP契約時の方が小さくなることが予想されます。
同会議の中で、政府は蓄電池の併設を一層強力に支援するとしています。
<参考リンク>
再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024.9.18)|資源エネルギー庁
再生可能エネルギー出力制御の長期見通し等について(2024.12.2) | 資源エネルギー庁
FIP転換のデメリット

金銭的な補償リスク(インバランス料金)がある
FIT制度とFIP制度の大きな違いのひとつに、インバランス料金があります。FIP制度では、電力を安定供給するための発電計画を提出しなければなりません。計画値と実績値が大きく異なった際にはその差を埋めるための費用(インバランスコスト)を支払う必要があります。このコストが大きくなると売電収益にも影響します。心配な場合には、アグリゲーターに管理を委託する、インバランス補償制度(保険)に入るなどしてリスクを回避する必要があります。
出力制御による機会損失がある
出力制御とは、電力の需給バランスに対応するために、電力会社が再エネ発電事業者に対して一時的に発電量を抑制する制度です。出力制御によってせっかくの売電機会を逃してしまうため、再エネ事業者にとって頭の痛い問題となっています。出力制御はFIT制度下でも行われてきましたが、FIP制度においても同様に行われます。
しかしFIP制度下では蓄電しながら電力単価の高いタイミングで売電することができるため、出力制御における影響をある程度コントロールすることができます。しかし、ただでさえ自然条件に左右される再エネが、出力制御による売電ロスも考慮しなくてはならないのはかなりのデメリットです。
近年、特に九州エリアでは出力制御による売電ロスが大きくなり、FIP転換を検討する事業者が増加しています。
設備の追加・運用管理によるコスト増がある
FIP制度では電気を売るタイミングを考慮しなくてはならないため、蓄電池が必要になります。また、発電の管理コストやタスクが増加します。それらをアグリゲーターに委託する場合は、委託費用も必要になります。売電によって受けられるメリットも大きいですが、これらのコスト増は発電事業者にとっては大きな課題です。次章では、これらの課題を解決するオムロン フィールドエンジニアリングのサービスをご紹介します。
オムロン フィールドエンジニアリングのFIP転関連サービス
出力制御による売電ロスを補填することで、FIP移行後もFIT同様の収入を保証する「FIT売電保証サービス」
オムロン フィールドエンジニアリングでは、前章でご紹介したようなFIPのデメリットや懸念を払拭するため、東京センチュリーとともに初期費用ゼロ・ランニングコストゼロで併設型蓄電池の設置・FIP移行手続きをサポートするサービスをスタートしました。売電に伴う手続きもサポートすることで、スムーズなFIP発電所の運用を実現します。
さらに出力制御による売電ロスを保証することで、本来のFIT収入を維持しながらFIP移行を完了していただくことができます。出力制御による売電ロスにお悩みだった事業者様にはぜひご注目頂きたいサービスです。
<参考リンク>
太陽光発電の出力抑制によるFIT売電ロスを補填する初期費用・ランニングコストゼロの「FIT売電保証サービス」開始について | ニュースルーム | オムロン株式会社
まとめ | FIP転換のお手続きはオムロン フィールドエンジニアリングへどうぞ
いかがでしたでしょうか。FIT制度を利用されている事業者様にとって大きな問題である「出力制御」。この問題に正面から取り組み、FIP転換をご検討されていらっしゃる事業者様をオムロン フィールドエンジニアリングは全力でサポート致します。
オムロン フィールドエンジニアリングは太陽光発電設備・蓄電池の設置・管理・運用について多くの経験と実績がございます。ご不明点、ご不安な点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
【執筆者情報】

脱炭素ソリューション.com 編集部
脱炭素ソリューション.comが運営する「エネタメ」は、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社のエネルギーマネジメントに関する豊富な実績とノウハウを活かした専門的な情報や、再生可能エネルギー、蓄電池、災害対策、省エネソリューション、補助金などのコンテンツを中心に、脱炭素化/カーボン・ニュートラルの取り組みに役立つ情報を発信しています。






